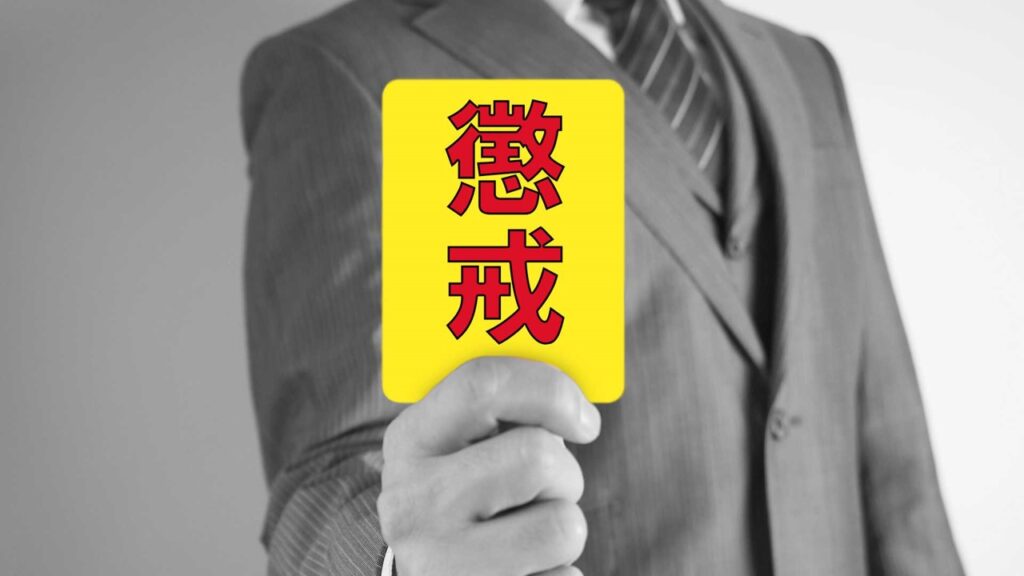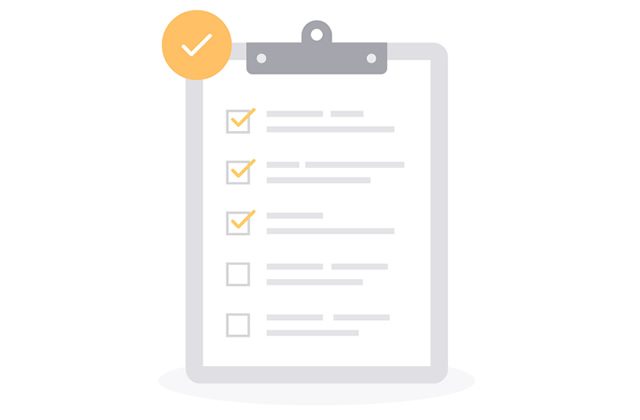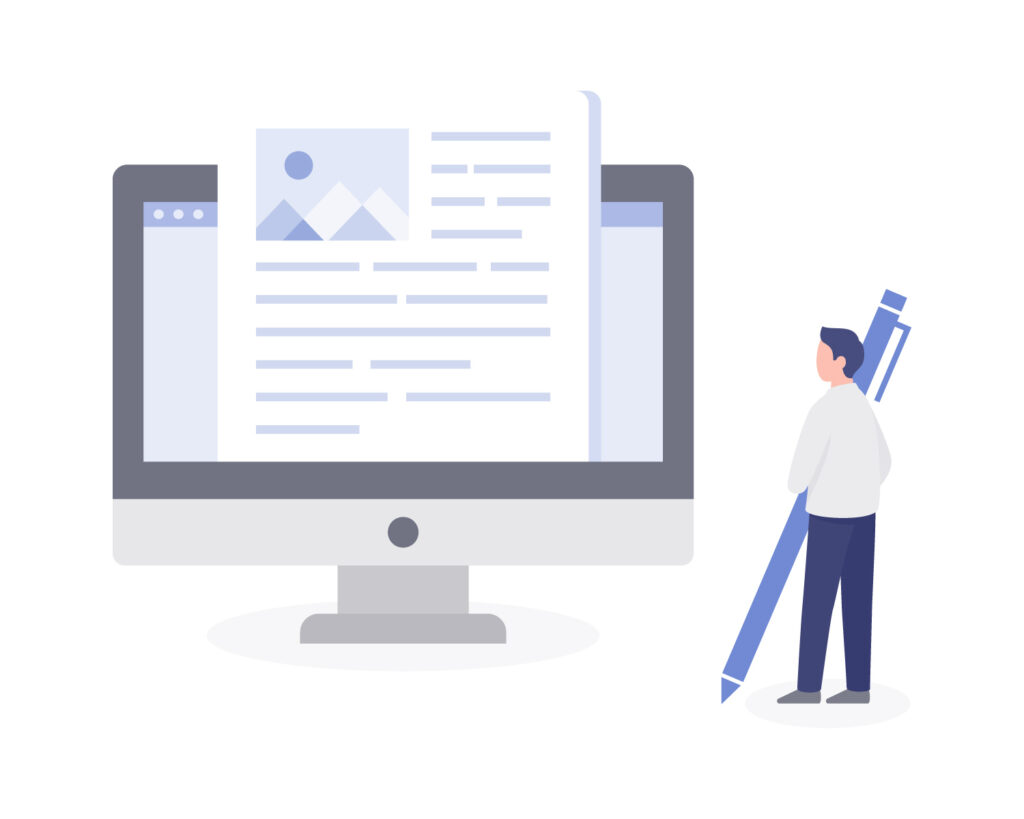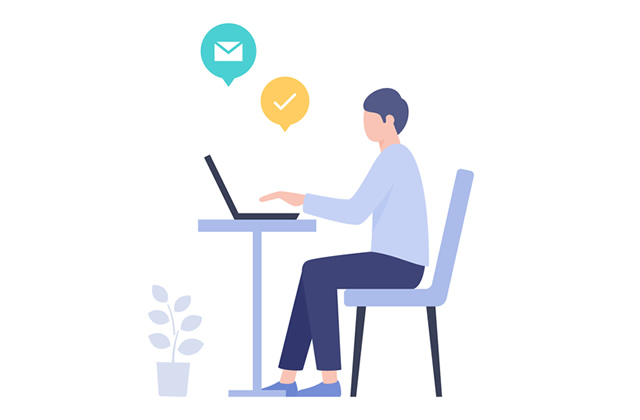当事務所の「戦略的」就業規則とは、これまで受けた労務相談のトラブル事例や経営者のこだわり、法的根拠、判例などを豊富に盛り込み、実際に労働トラブルになったときに会社を守ることができる就業規則に仕上げています。
就業規則の4つの役割
1.就業規則は、会社を守る唯一のツール
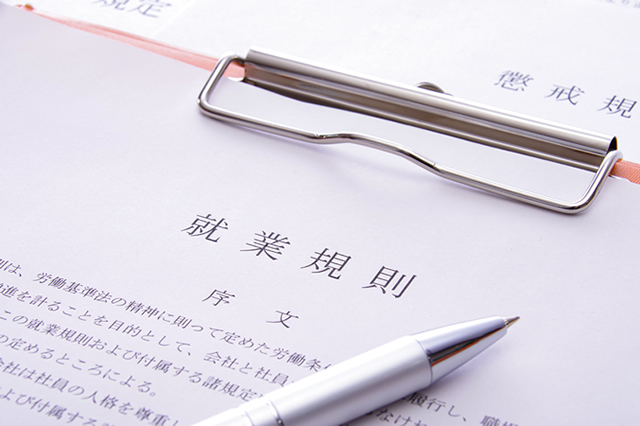
日本においては、社員を守る法律が充実している一方、会社を守る法律はほとんど無いに等しい状況です。
就業規則は、ただあればいいわけではありません。「会社を守る唯一のツール」ですからいざというとき会社を守る仕様になっているかどうかが重要です。起こりそうな労務トラブルや、社長がこれは入れて欲しいということは、個々の会社によって異なります。
当事務所では、会社の実態に合った条項を盛り込み、「会社を守る」という視点で労働問題に強い戦略的な就業規則を提供しています。
2.就業規則は、権利義務を明確にする

就業規則を作成し、社員に周知させることで、会社と社員の権利義務関係が明確になります。
自社に合った就業規則を作成することで、
「自分が何を求められているのか」
「どういう仕事をすべきなのか」
という意識を強めるきっかけになります。
3.就業規則は、社員の満足度と会社の収益力をアップさせる

確かな就業規則を作成することで、会社で守るべきルールを明確にするだけでなく、社員にとってより働きやすい環境を作ります。働きやすい環境で仕事をすることで社員のやる気をアップさせ生産性を高めて会社の収益力向上につなげることができます。
現在労働者が10人未満の会社であれば労基法上の作成義務はありませんが、会社と社員のために就業規則を作成しましょう。
4.就業規則は、助成金にも活用ができる

助成金をうけるためには、就業規則に助成金に対応する条項がなければなりません。
当事務所では、労働問題に強いだけでなく、助成金にも対応できる就業規則を提供しています。
戦略的就業規則のメリット
1.突然の退職で困らない
2.従業員の問題行動があったとき、就業規則を根拠に処罰が可能になる
例えば、従業員の問題行動があったとき、就業規則に定めていないと、会社として何もできませんが、戦略的就業規則では、様々な事例に対応した服務規程が規定されているため、労働トラブルや問題行動があったとき、就業規則を根拠として従業員を戒めることができます。
3.助成金にも活用ができる

助成金をうけるためには、就業規則に助成金に必要な項目と載せてはいけない項目があります。
ただ厳しいだけの就業規則では、助成金の受給要件を満たせません。
戦略的就業規則では、会社を守り、かつ助成金も受給できるバランスの取れた就業規則に仕上げます。
不十分な就業規則のデメリット
1.多額の未払残業代を支払うリスクがあります
退職すると義理がなくなり、実態と合っていない就業規則の不備をついて、退職した従業員が労働基準監督署にかけこみ、多額の未払残業代を払うことになる場合があります。1人だけでなく、何人もまとめて請求されると支払いきれず、倒産間近まで追い込まれたケースもあります。
2.情報漏洩や会社の悪口を言いふらされ、最悪は倒産というリスクがあります
就業規則の不備で、会社の重要情報を不正にもちだし、競合他社に転職されても全く咎めることができないケースもあります。そればかりか会社の悪口をSNSで言いふらされ、新しく求人活動をしようと思っても、悪い噂がたちこめ、誰も近寄ろうとせず、人材難で倒産というケースもあります。
3.優秀な社員から次々に辞めていくというリスクがあります
社員を懲戒処分するためには就業規則に記載しておかなければなりません。
勤務態度が悪い社員や問題社員に対し、不十分な就業規則の場合、問題行動に何も対処できず、会社が見てみぬふりをしていることに嫌気がさした優秀な社員が次々に辞めていき、会社の売上が大幅にダウンして事業が立ち行かなくなったケースもあります。
サービス内容
診断(リーガルチェック)
作成
見直し
運用サポート

当事務所で作成されたお客様なら顧問契約中は、就業規則の変更を何度でも無料にて対応します。
- 毎年のようにある法改正でも安心
- 助成金を活用する際にも対応可能
(他の事務所では、就業規則のメンテナンスや変更のつど、顧問料とは別に料金が発生することが多いようです。)
整備・改訂コンサルティングフロー例
- STEP1 現状分析
- 労働条件・慣行・ルール等の洗い出しと実態の運用チェック

- STEP2 記載事項の確認
- 就業規則の記載事項の確認
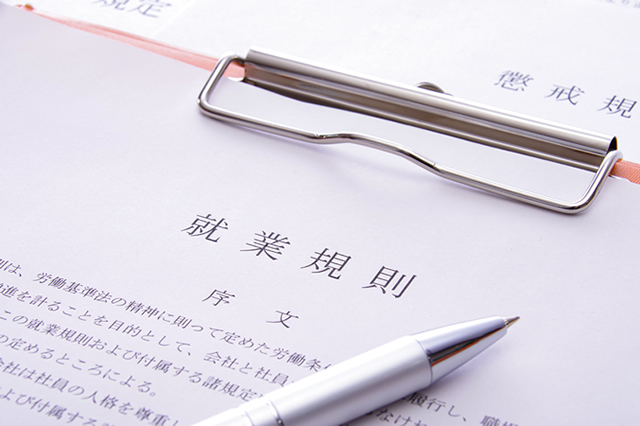
- STEP3 労働法規と整合性のチェック
- 労働法規に違反がないか確認

- STEP4 追加事項の検討
- 実態との差異や労働法規との差異の是正条項の検討

- STEP5 別規程の作成
- 本則以外の不足している別規程の整備

- STEP6 本則・諸規程の関連性のチェック
- 社内諸規程の関連性・整合性のチェック

- STEP7 社員代表選出・意見書の作成
- 法令の方法により代表者を選出・意見書の作成

- STEP8 社員説明会の実施
- 労働条件の変更や重要なルール変更の場合に実施

- STEP9 労働基準監督署への届け出
- 監督署を提出し、受付印を受領

作成可能な規程
1.就業規則
2.諸規程
有期契約社員規程、無期契約社員規程
(契約社員がまだいなくても、助成金を活用する場合は必要になります)
有期パートタイマー規程、無期パートタイマー規程
(50歳以上のパートタイマーがいる場合に使える助成金を活用する場合は必要です)
定年度再雇用者規程、嘱託社員規程
(60歳以上の社員がいる場合が1年契約になるため、ほとんどの企業で必要です)
賃金規程、退職金規程
育児休業規程、介護休業規程
出張旅費規程
(経営者の可処分所得を増やすためにあると便利です)
秘密保持規程
(企業秘密や情報漏洩が心配な場合にあると便利です)
慶弔見舞金規程
在宅勤務規程
ハラスメント規程
兼業・副業規程
社有車管理規程
これらは全て作成する必要はありませんが、貴社のニーズに合わせて、その他規程についても、ご要望に応じて作成します。
サポート内容
1.専用ファイルで納品(CDデータ付)
2.関連書式提供
3.労働基準監督署へ提出
価格表